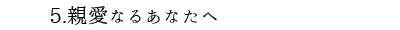
母を見失ったかのように叫ぶ少年の声が、誰かの名前を呼んでいた。それが本当に母親の名であったのか、見当をつけることもかなわない。冷気は着実にシルヴィアの指先をむしばんで、口から空気を吐き出させようとする。あきらめのなかに死を覚悟するときは、いつも自分の弱さに愛想が尽きていた。
何度でも夢を見る。彼を呼べたことは、一度としてなかった。
ちちち、と鳴きかわす鳥が、窓から影を落としていた。窓枠に立てかけた手紙の花は、もうすっかり枯れてしまっている。シルヴィアはそれを、あとが残らないようにと丁寧に引き抜いた。
バジルは約束を果たしたのだ。シルヴィアの言葉に腹を立てたとしても、彼女の頼みだけはたしかに聞き届けた。そういう少年だった。
今日のうちに、彼らはスェルタを発つことになるだろう。いまごろは着々と準備を進めているはずだと考えて、シルヴィアの鼻はつんと痛んだ。
「ごめんなさい」
彼に謝る資格さえ、自分にはないというのに。
手早く着替え、ベッドを整えて、髪をリボンでくくったあとに帽子をかぶる。窓に映した自分の姿は、抱く痛みも忘れてしまったかのようだった。
クローディアにあてられた手紙を、封筒の角も擦らないように服の内側にしまいこむ。残った一通はシルヴィアの手元で留まった。結局想いのひとつも口に出せなかったシルヴィアの代わりに、バジルがどんな言葉を綴ったのか――ちらりとだけ想像して、首を振る。
手紙の両端を手に取り、中央から二つに引き裂いた。
そうして四つに、八つに。やがて散り散りになった紙の切れはしを窓の外の風に任せる。やわい熱気をはらんだ夏の空気が、手の上をさらっていった。ゆく先を見送ることもせずに窓を閉じる。ぴしゃり、という音がやけに耳に残った。
シルヴィアに残る仕事はもうひとつ。あとひとつだけだった。
扉を叩いた下仕えの娘の呼びかけに、クローディアは厭う様子を見せなかった。
朝日を浴びた長い髪が、刈りたての麦穂のように輝いている。彼女を指して豊穣の女神だと称する声があったことを思い出しながら、シルヴィアは一時、その色に見とれていた。
彼女の心根が、空を目指す若芽のようにまっすぐであることも知っている。人前に顔を出さずとも彼女は愛されていた。彼女やテオの持ち帰ったいくつもの花冠がその証だ。
「おはよう、シルヴィア。昨日は楽しめたかしら」
いつになっても口を開かないシルヴィアに、クローディアがほほ笑みかける。シルヴィアは曖昧に笑うだけだった。
見れば、クローディアの顔にはかすかな疲れが残っている。夕暮れどきまでに屋敷に戻ったとはいえ、久方ぶりの外出は彼女の身にこたえたのだろう。
「お疲れさまでした、お嬢さま」
「疲れただなんてとんでもない、すてきな一日だったわ。あなたの勧めにしたがってよかった。テオもお礼を言っていたわよ」
慣れないながらもゴートルードの言葉で話そうとする青年の姿が、村人に受け入れられたのだ。彼らの周りには終始人だかりができていた。まるで花瓶のようだったふたりの姿をシルヴィアも覚えている。
「……テオさまは、スェルタの領主になられるんでしょうか」
クローディアが目を丸くする。
そうね、と彼女がくちびるを動かしたのは、それからすこしの間を置いてからだった。
「テオはロマルタで爵位をもつ家に生まれた人なの。そしてここスェルタは、ゴートルードとの国境に位置する領。だからこの結婚は、ロマルタがゴートルードでの力を強めるためのものとも、国家間の親交を図るためのものとも言われているわ。……わかるかしら。政略結婚と言ったほうが手っ取り早いかもしれないわね」
沈んだシルヴィアの表情を伺って、クローディアは安心させるように目を細めた。
「エスマルヒ――テオのご実家の名前はわたしも知っているようなものだったから、最初はどんなに高慢なひとがいらっしゃるのだろうと思っていたの。そうしたら彼でしょう? 言葉も不満足なのに、身ひとつで飛び込んでくるのだもの。張っていた気もゆるんでしまって」
「……わかります」
シルヴィアは目元だけで苦笑する。
川の水に濡れることも厭わず、シルヴィアを助けに飛び込んだ。意気消沈していたシルヴィアを気にかけて、足しげく料理人のもとへと通った。――あれはきっと、彼自身のやさしさなのだ。騎士の魂でも、貴族の礼節でもない。
似合いの二人だ。すとん、と胸に落ちてしまった納得に、シルヴィアは身の締めつけられるような思いにかられる。隠したままの封筒が熱を持った。
「お嬢さまとテオさまは、きっと、幸せなご夫婦になります。皆が祝福して、愛するような、そんなご夫婦に。けれど」
切り捨てられる想いがある。それを知っている。押し付けのお節介だと理解していても、シルヴィアには手放しで祝うことができなかった。ひとつ、ふかく息を吸って、シルヴィアは顔を上げる。
「お嬢さま。お渡ししたいものがあります」
宛名も差出人も書かれていない手紙だ。シルヴィアから封筒を受け取って、クローディアは不思議そうにまばたきをした。
「これは?」
「私の、……友人から預かったものです。お嬢さまにお届けしたいと。手紙を運ぶことを持ちかけたのは私です、お叱りは後ほどいくらでも伺います。でも今は、どうかそれをお読みになってはいただけませんか」
「内容について尋ねてもいいのかしら」
シルヴィアは口をつぐむ。クローディアはそうと一言つぶやいて、文机からペーパーナイフを拾いあげた。封を裂く音がしずかな部屋にこだまする。取り上げられた二枚の手紙を、彼女は宝石のように両手でささげ持った。
クローディアの目が紙の上を走るあいだ、シルヴィアは視線を逸らしたまま黙りこくっていた。便箋がこすれ合い、二枚目の結末に辿りついたクローディアは、文面を反芻するようにまぶたを下ろす。
「シルヴィア」
声は静かだった。親に叱られた子供のように、シルヴィアの肩が震える。はい、と返事をすると、クローディアは長い睫毛に覆われた目をひらく。
「これを書いたのはどんな人なのかしら」
問いかけに、シルヴィアはわずかにうろたえる。
バジルの口を割った告白が脳裏をよぎった。あれはクローディアの歩く道の小石であることを厭わない者の言葉だった。封筒と同じように、彼の名前が記されていなくてもおかしくはない。
「今日、スェルタを出ていく人です」
別れも告げられないままだった。シルヴィアに残ったしこりは、きっといつまでも酸い記憶となって残り続けるのだろう。
「あなたにとっては?」
「幼なじみです。物心のつく前から一緒でした」
声に迷いが生まれる。クローディアの眼差しは、胸のうちを透かすようにシルヴィアへと向けられていた。耐えられなくなって力なくうつむく。
「ずっと、友人でいました。……そのはずです。そのはず、でした」
沈黙の前にさらされたとき、自分の心は、その手に編まれた花冠よりももろかったのだと知った。
積もり積もった悔恨が、ようやく形を取り始める。彼に渡すべくは、花冠でなくてもよかったのだ。がんじがらめのそれを解いて、ひとつの花束を作ればよかった。素直な言葉でじゅうぶんだった。
「好きでした。好き、だったんです。……なのに、ひどい嘘をついて、私……!」
一言を。たった一言を、どうして伝えられなかったのだろう。
涙はぼろりとこぼれだして、おさえつけることもかなわない。そんな自分に嘘をつき通すことができるはずもなかった。他人も自分も傷つけて、はじめて体裁を取り繕う嘘など、吐き続けられるわけがなかったのだ。
クローディアは指先で便箋の角をはじく。続いて彼女の唇がつむいだのは、打って変わって穏やかな声だった。
「この手紙のあて先を教えてあげましょうか、シルヴィア」
赤い目をこすってクローディアをあおぐ。
――あなたよ、と。
告げられた言葉を、うまく飲み込めなかった。
「赤いリボンのあなた。そう何度もくり返されるのに、私のことだなんて思えないわ。それとも、村にはほかに赤いリボンをつけた女の子がいて?」
声が出ない。首を振ったシルヴィアに、クローディアは手紙をひらりと揺らしてみせた。
「嘘をつくのは苦しかったでしょう。けれどあなたの想うこの子も、ずっと嘘をつき続けたの。……ねえ、シルヴィア。もうそれも終わりよ。もしももう一度会えるとしたら、あなたは彼にどんな言葉を伝えるのかしら」
シルヴィアのあごが震え、言葉にならない嗚咽がもれる。クローディアはそれを見下ろして、はっきりとうなずいた。
「まだ間に合うわ」
シルヴィアの肩を叩き、扉を開く。こもった空気が流れだし、
「テオ! ……テオは起きていて!?」
そうして飛び出したのは、シルヴィアが聞いたこともない大声だった。
ちょうど近くを歩いていたのだろう、早足で姿を現したテオが、シルヴィアに目を止める。顔面には珍しく困惑がにじんだ。
「朝からなにがあったんだ、クローディア。シルヴィアはどうして」
「おしゃべりはあとよ。馬を走らせて。いますぐ彼女を村まで運んでちょうだい」
早口で言ったあと、続けざまにロマルタ語が発される。同じ内容をくり返したのだとシルヴィアが気づいたのは、テオが首をひねったときだった。いいからとその背を押して、クローディアはシルヴィアをふり返る。
「いいわね、シルヴィア。今度こそ届けるのよ。あなたの言葉、あなたの口で。……もうあて先を間違わないように」