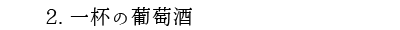
シルヴィアは踊り場の窓を開き、降り注いだ日の光に目を細める。階段に足を踏み出した女性――領主の娘クローディアが、彼女を認めてやんわりとほほ笑んだ。
「おはようシルヴィア。またよろしくね」
「はい、お嬢様。おはようございます。今週もせいいっぱいお勤めいたします」
小さなスェルタ領を治める領主に、仕える使用人の数は少ない。乳母のデボラに料理人のガストン、そしてシルヴィア。片手の指の数にも足りない彼らが、家事のすべてを担っていた。
そのためシルヴィアの午前中は大部分が掃除に費やされる。クローディアが立ち去るのを見送ってから、ようしと気合を入れて袖をまくりあげた。まずは二階、続いて一階。廊下を掃き終える頃には太陽も高くに上っているだろう。しかしいざシルヴィアが箒を握り直したところで、廊下の半ばまでを歩いていたクローディアがくるりと踵を返した。
「そうそう、伝え忘れていたわ。おとといから屋敷にお客様がいらっしゃるの。いまは二階の角部屋を使っているから、そちらのお掃除はあとにしてもらえるかしら」
シルヴィアはどきりとして息を止める。あのう、と探るように問いかけた。
「もしかして、ロマルタからいらっしゃった方でしょうか」
「あら、よく知っているのね。もう誰かから聞いていて?」
「いいえ、おとといちょうどお会いしただけで……お名前も伺えなかったのですけれども」
溺れかけたことは伏せておく。クローディアはシルヴィアの言い分を疑うこともなく、そう、とうなずいた。
「テオというのよ。テオ・エスマルヒ。まだこちらの言葉には慣れていないから、スェルタにいらっしゃるのも勉強ついでだと言っていたわ。ロマルタの公用語を使っていたでしょう?」
「はい」
異国の言葉も、クローディアには難解なものではないのだ。現にクローディアが携えている本もゴートルードのものとは違う言語で書かれているらしい。自国語の読み書きさえ満足にできないシルヴィアにとっては、どこのものと見当をつけることさえできない文字だった。
「明日は人を呼んで、彼を迎えるパーティーを開こうと思っているの。あなたにも給仕をしてもらうことになるわ。急な話になってしまうけれど、お願いね」
「かしこまりました」
小気味いい返事の裏には、シルヴィアの空元気が見え隠れする。クローディアはそこで声色を和らげて、「今日の午後は、詩集の続きに入りましょうね」と告げた。途端顔をはね上げたシルヴィアにくすりと笑って、声をひそめる。
「デボラには内緒よ。見つかったら怒られてしまうから。お菓子はあなたに運んでもらうようにするわ」
乳母を務めるデボラは、屋敷に仕える使用人の年長者でもあった。ともなれば数少ない使用人たちをまとめ上げる役割が彼女に任せられるのも当然で、その小言は主である領主やその夫人、娘のクローディアにさえ向けられることがある。
使用人になったばかりの幼いシルヴィアをしつけたのもデボラだった。失敗を叱る彼女の声には、有無を言わせぬ響きが混じるのだ。シルヴィアはぶるりと身を震わせて、くり返しうなずいた。
今度こそ階段を下りていくクローディアを見送ると、箒を握る手にも力がこもる。約束の午後までには掃除と洗濯を済ませなければならない。ふっと息を吐き出して、一足飛びに階段を駆けのぼっていった。
トレイの上には一切れのりんごのカントリーケーキ、エスプレッソコーヒーを淹れたポットに、葡萄が描かれたカップ、揃いのソーサー。角砂糖の詰まったガラスのポットは、クローディアには本来必要のないものだ。にもかかわらずトレイに載せられているそれは、菓子を用意した料理長の心遣いのあらわれだった。
トレイを片手で支え、シルヴィアはクローディアの部屋の扉を叩く。返事を待って踏み入ると、窓から吹き込んだ風がそっと頬を撫でていった。
「お菓子をお持ちいたしました」
「ええ、ありがとう」
窓際に立つクローディアの面差しには、かすかな影がよぎっていた。しかしシルヴィアがまばたきをするうちにそれも薄れて消えてゆく。窓をしめ直し、カーテンを引くと、クローディアはソファに腰を下ろした。
机にカップと菓子とを並べながら、シルヴィアはちらりとクローディアをうかがう。彼女以外の貴族の女性を見るのは、ときおり屋敷で開かれるパーティーの場においてのみだ。彼女らに比べクローディアの体はほっそりとして頼りない。屋敷を出ることが少ないのもそのためだった。
「お外を――」
見ていらしたんですか。うかつに問いかけた唇を噛みしめる。クローディアが続きを促すので、シルヴィアはふるふると首を振った。
「まだ外は肌寒いですから。暖かい格好をなさってくださいね」
「デボラと同じことを言うのね。いまは日があたっているから平気よ。温かい飲み物もあることだし、ね」
シルヴィアの注いだコーヒーからは、ゆるり、芳しい香りが匂いたった。煮りんごがつやめくケーキに、クローディアは顔をほころばせる。そうして机の陰に隠していたカップを取りだした。
「さあ座って、シルヴィア。コーヒーは二杯分あるかしら」
「はい、きっと」
「角砂糖は確かふたつね。前回ひとつに挑戦して失敗したときのこと、まだ憶えているわよ。眉をこんなにゆがめて、すっぱい顔をして」
「お嬢様!」
シルヴィアが唇をとがらせると、クローディアは目を細める。彼女はごめんなさいねと言って笑った。
「背伸びはしなくていいのよ。あなたはあなたのままでいいの。そういえばきついお酒の香りもだめだったわね、明日の用意のときにはガストンにそう伝えておきましょうか」
「そ、そこまでしていただくわけにはまいりません」
一使用人に仕事を拒む権限はないのだ。近隣の領からも貴族が集まってくるともなれば、彼らにつき従う従僕や侍従に、給仕を手伝われることもあるだろう。主催のスェルタ領伯に仕えるシルヴィアの不手際は、主である彼の顔に泥を塗ることにもつながる。
「私が気をつけることですから、どうかお気になさらないでください」
クローディアは無念そうに眉を下げる。けれどもシルヴィアの心は変わらないと見て取って、最後には首を縦に振った。コーヒーを口に含み、ほうと息を吐く。
「ロマルタのお酒も取り寄せると言っていたから、気にかかったの。その様子なら心配は必要なさそうね。……そうだわ、お酒といえば」
ふいにクローディアが紡いだのは、ワインに寄せた
詩人の目から描かれる葡萄摘みの少女は、朝も、昼も、日が暮れるまで農作業に精を出す。流れた汗は夕陽にきらめき、闇に濁ってしたたり落ちていく。それをなにより尊い葡萄酒として歌う詩だった。
呆けるシルヴィアの前に二度同じ詩をくり返し、クローディアは懐かしむように息をつく。
「幼いころに読んで、わたしには理解のできなかった詩だったの。あのころは……いいえ、いまだって、わたしは汗が輝くところなんて見たことがなかったから。あなたなら作者の気持ちがわかるのかしら」
「ええと」
畑仕事に向かう両親の姿を思い出し、シルヴィアは渋い顔をする。
「同じものを見たことはあると思います。でも、それを葡萄酒だなんて思ったことは一度も。……作者はきっと、農作業をするような方ではないんですね。お生まれが高貴で、畑の娘を後ろから見つめているような――」
シルヴィアの言葉を遮ったのは、クローディアの笑い声だった。こらえきれなかったとばかりにくつくつと笑い続ける彼女を、シルヴィアはぽかんと口を開けて眺める。
「私、なにかおかしなことを言ったでしょうか」
「いいえ、なにも。ごめんなさいねシルヴィア。作者を知っているものだからつい。……生まれが高貴で、娘を後ろから見つめている。そうね、ふふ」
シルヴィアの言葉を、クローディアはたいそう気にいった様子でくり返す。ひとしきり笑い終えてから、彼女はケーキのかけらを口に運んだ。
「ちょうどいいわ。今日はいまの詩を書き写してみましょうか。綴りのむずかしい単語も使われていないから、いいお勉強になるわ」
週に数度、秘密の休憩に続けられる勉強会こそ、シルヴィアが部屋に招かれた理由だった。開かれたままの本にシルヴィアが興味を示したのが一年前、クローディアが気まぐれにアルファベットの綴りを教えたのも同じ日だ。もはや恒例になった秘めごとの存在を知るのは、二人をのぞけば寡黙な料理長を残すのみである。
ケーキとコーヒーがあらかた腹に収まってから、クローディアは紙とペン、インクの壺を持ち出した。彼女の手に綴られる文字の羅列を、シルヴィアは食い入るように見つめていた。
「前に言っていた代書人の息子さんには、字を習っていることを教えたのかしら」
ペンをシルヴィアに預けてしばらく。ふいにクローディアが問いかけた。詩を書き写していたシルヴィアは、思わず口元をこわばらせる。震える指を撫で、強いて呼吸を整えた。
「まだです。あんまり中途半端だと、笑われてしまうので」
「一緒に勉強することはしない?」
「私がですか?」
問い返しながら、バジルと並んで机に向かう自分の姿を思い浮かべる。シルヴィアは力なく首を振った。
「きっと邪魔になります。私と違って、あの子は働くためにお勉強をしているから」
それに、と続けかけた口をつぐむ。続きを言葉にするつもりはなかった。
彼が望む居場所がクローディアのそばである以上、バジルの隣にいるのも、クローディアとともに午後のひとときを過ごすのも、シルヴィアであるべきではないのだ。なんとはなしに不安を覚え、シルヴィアはエプロンのすそを握りこむ。
――共犯者。自分で言い放った言葉の重みが、そのときはじめて、両肩にのしかかったような気がした。